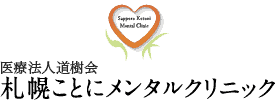9月も残すところあとわずかとなりました。街路樹も少しずつ色が変わり、秋の景色が段々と近づいているようです。
秋といえば、食欲の秋、読書の秋、スポーツの秋など、様々な話題が取り上げられますね。美味しい食べ物も増える時期ですし、暑さも和らぎ運動もしやすくなります。そして、読書といえば、個人的には漫画が得意ですが、文学など活字に触れることも注目される時期です。
最近では、読書も紙ではなく画面で行うことが主流になってきております。中には聴く読書もあるぐらいです。ネットブックが出始めた頃は、なんとなく本は紙で読みたいものと思いながら利用していましたが、今ではその便利さが上回り、様々な書籍を画面で読むようになりました。おそらくそうなっている方も少なくないでしょう。
雑誌や書籍のサブスクリプションも登場し、定額で好きなときに興味のある本や雑誌を読むことができます。移動中やちょっとした時間潰しにも手軽に利用できるため、利用する機会も増え、次第にページをめくるのではなく、スクロールして読むことにも慣れてくると、当初のような違和感もなく、スマホで読書が自然になってきています。
心理療法でも慣れというのは、治療上利用する動物に備わった適応力の一つです。心理療法ではよく恐怖に対する治療に用いていますが、技術の進歩にも慣れというものは生じていきます。
しかし、場合によっては慣れが生じにくい、生じないということもあります。人間であれば慣れたくないと抵抗することもあるかもしれません。私も昔から大好きなとあるバスケットボール漫画は、今でも紙で読みたくなります。何度読んでも、昔と同じように興奮、感動してしまうその漫画は、やはり画面をスクロールするよりも、紙をめくって読みたいなと思います。
読書の秋なので、久しぶりに全巻読み直してみようかと思う、この頃です。