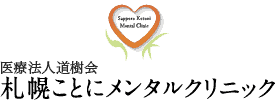札幌は秋から冬にかけて日照時間が短くなり、朝起きづらい、気分が沈む、甘い物を過食して体重が増えるなどの変化が出やすくなります。これらは季節性うつの典型的なサインです。今回は自宅でできる対策と、医学的に知られている発生の仕組みをまとめました。
札幌の冬に多い季節性うつとは
秋冬の光量低下が引き金となり、意欲低下や過眠、炭水化物への渇望が強くなるタイプのうつ状態です。春になると自然に軽快することが多いのが特徴です。欧米や北国では「冬季うつ」と呼ばれ、札幌のような高緯度地域で比較的多くみられます。
日本でも 厚生労働省の公式サイト で季節性うつ病の特徴や治療法が紹介されています。
季節性うつ病の発生機序と札幌の光環境
研究によれば、主に次の要素が関与すると考えられています。
-
体内時計の遅れ
日照不足で朝の光刺激が減り、概日リズムが後方にずれることで、起床困難や昼間の眠気が生じやすくなります。 -
メラトニン分泌の変化
暗い時間が長くなるほど、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌が過剰・延長し、日中の活動性を低下させます。 -
セロトニン機能の低下
光刺激不足により脳内セロトニンの合成や神経活動が落ち込み、抑うつ気分や過食傾向につながるとされます。 -
遺伝的要因
全員に起こるわけではなく、感受性に個人差があります。セロトニントランスポーター遺伝子の多型などが関与すると考えられています。
海外では 米国国立精神衛生研究所(NIMH)の解説 にも、発生メカニズムや治療法の詳細がまとめられています。
札幌の光環境と体内時計の乱れ
朝の光は体内時計のリセット信号です。秋冬はこの信号が弱くなるため、起床時間が後ろにずれ、昼の眠気や夜更かしが起こりやすくなります。
「朝に強い光、夜は光を弱く」が基本原則です。
今日からできるセルフケア
-
起床後1時間以内に屋外や窓辺で自然光を浴びる
-
毎日同じ時刻に起きて朝食をとる
-
夜は照明を落とし、就寝前のスマホ使用を控える
-
平日と休日の起床時刻差を1時間以内にする
-
有酸素運動を週3回以上、夕方より前に行う
医療でできること
症状や生活背景を評価し、光療法や睡眠覚醒リズムの調整、必要に応じて薬物療法を組み合わせます。近年は抗うつ薬や認知行動療法の併用も有効とされています。
受診の目安
-
2週間以上、気分の落ち込みや過眠・過食が続く
-
仕事や学業、家事に支障が出てきた
-
朝起きられず遅刻が増えた
-
春になっても改善が乏しい
よくある質問(FAQ)
Q 光療法はどれくらいで効果が出ますか?
A 多くは1〜2週間で変化を実感しますが、個人差があります。
Q ビタミンDは関係しますか?
A 冬季の欠乏が関与する可能性が指摘されており、血中濃度を測定しながら補充することがあります。
Q 季節性うつと通常のうつ病の違いは?
A 季節性うつは秋冬に悪化し、春に自然に軽快しやすい周期性があり、過眠・過食が目立つ点が特徴です。通常のうつ病は季節に関わらず持続し、睡眠や食欲は減少傾向を示すことが多いなど、症状の出方が異なります。
ご相談は予約ページから受け付けています
気分の変化に気づいたら、迷わずご相談ください。早期の対応が、春を軽やかに迎える鍵になります。