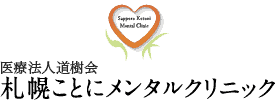札幌も朝晩はぐっと涼しくなり、秋の気配を感じる季節になってきました(*^^*)気温差や日照時間の変化は、心身に大きな影響を与えます。季節の変わり目に「なんとなく気分が落ち込む」「疲れやすい」と感じる方は少なくありません。本記事では、医学的な視点と日常生活でできる工夫の両方から、季節の変わり目に役立つメンタルケアについて解説します。
季節の変わり目に起こりやすい心の変化
-
気分の落ち込みや憂うつ感
日照時間が短くなると、脳内のセロトニン分泌が減少し、気分の落ち込みにつながることがあります。さらに、光の刺激が減ることでメラトニンの分泌リズムも乱れやすくなり、睡眠の質や昼夜の体内時計に影響を及ぼします。その結果、気分の低下や倦怠感が長引く要因となることがあります。 -
疲れやすさ・集中力の低下
寒暖差による自律神経の乱れが、倦怠感や注意力の低下を引き起こすことがあります。 -
睡眠リズムの乱れ
昼夜の寒暖差や日照時間の変化で、眠りが浅くなったり、寝つきが悪くなるケースがあります。 -
身体症状の増加
頭痛・胃腸の不調・動悸などが「心の不調」のサインとして表れることもあります。
専門的にみたメンタルケアのポイント
自律神経の安定化
規則正しい生活リズムを保つことは、自律神経の安定につながります。特に「起床時間を毎日そろえる」ことが効果的です。
光とメラトニンの関係
朝の光を浴びることで体内時計がリセットされ、夜には自然な眠気を誘うメラトニンが分泌されやすくなります。秋冬は日照時間が短くなるため、意識的に朝日を浴びることが推奨されます。
栄養と脳の働き
うつ症状との関連が指摘される「葉酸・ビタミンB群」「オメガ3脂肪酸」などをバランスよく摂ることが大切です。特に秋鮭や秋刀魚、きのこ類はおすすめの食材です。
(参考:厚生労働省「健康づくりのための睡眠指針」)
日常生活でできるセルフケア
規則正しい生活習慣
・起床・就寝の時刻を一定に保つ
・朝食をしっかり取ることで体内時計をリズム良くスタートできる
適度な運動
・ウォーキング、ヨガ、ストレッチなど軽度の運動が効果的
・「汗をかく運動」よりも「続けられる運動」を優先
食欲の秋を活かした栄養バランス
・旬の野菜や魚を意識して取り入れる
・糖質・脂質に偏らないよう注意する
気分転換と休養
・短時間でも趣味やリラックスの時間を設ける
・深呼吸やマインドフルネスなどで心を落ち着ける
相談を検討する目安
-
気分の落ち込みや不眠が2週間以上続く
-
仕事や学業に支障が出ている
-
食欲・体重の変化が大きい
-
不安や焦燥感が強く、コントロールできない
こうした症状が続く場合は、一人で抱え込まず、信頼できる人や専門機関に相談してみることも大切です^_^
(参考:国立精神・神経医療研究センター「こころの健康」)
まとめ
季節の変わり目は、心と体に少なからず影響を与えます。自律神経の乱れやセロトニン・メラトニンの働きの変化は誰にでも起こりうるものです。日常の小さな工夫で症状を軽減できることも多いため、まずは生活習慣を整えることから始めてみましょう(*^^*)
どうか無理をせず、できることから少しずつ取り入れて、心地よい秋をお過ごしください。