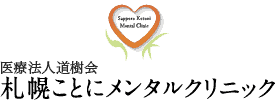紅葉も進み、本格的な秋が訪れています。寒さも徐々に厳しくなり、先日は手稲山でも初冠雪が記録されました。冬が段々と近づいてきていると感じる季節ですね。
過去のブログでも取り上げたように、冬季は季節性のうつ病と呼ばれる病状があります。日照時間の短縮の影響が要因と言われておりますが、冬になると気分が沈みやすくなるというようなことが起こります。一般的にはうつ病などの精神的な病気には、人間関係や多忙など日常的なストレスにより引き起こされるイメージがありますが、必ずしもそうではないということになります。
他にも女性に限られますが、生理周期やホルモンバランスにより気分が沈みやすくなることもよくみられます。また性別に関わらず、十分に栄養が取れない時期が続き、低栄養状態になったときにも気分が沈みやすくなります(その他にも色々な変化があります)。
こうした、ある時期やある条件が持続すると生じる抑うつ気分については、時期や条件が解除されると自然回復するという特徴があります。春になると改善したり、栄養状態が回復すると気分も安定するといった変化が生じます。したがって、必ずしも専門的な治療が必要というわけではありません。
ただし、時には治療が必要となる場合があります。北海道の冬季は長いですし、定期的に気分が沈むということも日常生活が送りにくくなるきっかけになることもあります。そのような場合には、精神科や心療内科、時には婦人科、内科といった医療機関に相談をすることが推奨されます。治療は主に薬物療法がとらえます。うつに効果が認められている薬剤や漢方薬などが用いられることもあるようです。冬季のうつには薬物療法だけでなく、光療法と言われる治療も効果があると言われています。
ある時期や条件で気分が沈みやすい傾向があると感じられるときには、一度専門的なご相談を考えてみるとよいかもしれません。